一罪の一部起訴の可否
問題の所在
一罪の一部起訴とは、1個の刑罰権を発生させる原因となる一罪の一部についてのみ公訴を提起することをいいます(『リーガルクエスト刑事訴訟法(第2版)』213頁)。
- 単純一罪の一部起訴
- 結合犯の一部起訴
- 強盗罪を恐喝罪、殺人罪を傷害致死罪、共同正犯を幇助犯として起訴
- 既遂罪を未遂罪として起訴
- 加重犯の一部起訴
- 科刑上一罪や包括一罪の一部起訴
証拠が足りなくて立証できない等の理由で、立証できない部分について起訴しないことは「一罪の一部起訴」の問題ではありません。
例えば、以下の場合、「一罪の一部起訴」の問題ではありません。
- 強盗罪だと思っていたが、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫の嫌疑が不十分であるため、恐喝罪で起訴する。
- 業務上横領罪だと思っていたが、業務性の立証ができないため、単純横領罪で起訴する。
「一罪の一部起訴」の問題は、起訴すれば有罪判決が得られるとの確信に達する程度の心証を得るだけの証拠がある(一罪の立証が可能)のに、敢えてそのうちの一部についてだけ起訴することができるかという問題です。
問題の所在は、一罪の一部起訴を認めると、訴因制度の下では裁判所の審判対象が検察官の設定した訴因に限定されるため、実体的真実発見の要請に反するのではないかという点にあります。
公訴不可分の原則や実体的真実発見の要請に反する結果になること等を理由に一罪の一部起訴を認めない消極説もありますが、判例・通説は積極説です。
以下、積極説を見ていきます。
原則
①刑訴法は訴因制度を採用しており、訴訟物の設定は検察官の専権であること(訴因設定権)
②検察官は、起訴に足る嫌疑が認められる場合であっても、起訴便宜主義の下で、事件そのものについて公訴を提起しないこととする裁量権を有していること(広範な訴追裁量権限、248条)
③裁判所の判断は訴因に拘束されること
に鑑みると、検察官は、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して、一罪の一部についてのみ公訴権を行使することも原則として許されると解すべきです。
刑事訴訟法248条(起訴便宜主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
最決昭和59.1.27は、公職選挙法の供与罪と交付罪に関して、供与罪が成立するときは交付罪は供与罪に吸収されることを前提に、「検察官は、立証の難易等を諸般の事情を考慮して、甲を交付罪のみで起訴することが許される」としました。
最判平成15.4.23は、横領後の横領の事案において、「所有権移転行為について横領罪が成立する以上、先行する抵当権設定行為について横領罪が成立する場合における同罪と後行の所有権移転行為による横領罪との罪数評価のいかんにかかわらず、検察官は、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮し、先行の抵当権設定行為ではなく、後行の所有権移転行為をとらえて公訴を提起することができるものと解される」としました。
最決平成15.10.7は、「実体的には常習特殊窃盗罪を構成するとみられる窃盗行為についても、検察官は、立証の難易等諸般の事情を考慮し、常習性の発露という面を捨象した上、基本的な犯罪類型である単純窃盗罪として公訴を提起し得ることは、当然である」としました。
例外
もっとも、検察官の訴因設定権・訴追裁量権の行使は、合理的裁量に基づくものでなければならず(最判平成4.9.18)、一罪の一部起訴が不合理な裁量によるものであるときは、当該一部起訴は違法・無効になると解すべきです。
一部起訴が不合理な裁量による場合には、裁判所は公訴棄却(338条4号)すべきとする見解が通説です。
チッソ水俣病事件(最決昭和55.12.17)では、不平等な公訴提起が公訴権の濫用として違法とならないかが問題になりました。最高裁は、「検察官は、……公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を認められているのであって、公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱によるものであったからといって直ちに無効となるものではないことは明らかである」としたうえで、「検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが、それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである」とし、「審判の対象とされていない他の被疑事件についての公訴権の発動の当否を軽々に論定することは許されないのであり、他の被疑事件についての公訴権の発動の状況との対比などを理由にして本件公訴提起が著しく不当であったとする原審の認定判断は、ただちに肯認することができない」としました。
かすがい外し
住居に侵入し、室内にいた2人を殺害した事案で、住居侵入罪と2つの殺人罪を起訴するとかすがい理論によって科刑上一罪になるのに対し、住居侵入を除いて起訴すると2つの殺人罪が併合罪になります。
このようにかすがい理論により科刑上一罪になる複数の犯罪について、かすがい部分を除いて起訴することは許されるでしょうか。併合罪で処理されると量刑が重くなり被告人に不利益であるため問題になります。
起訴された事実(殺人罪2つ)の処罰自体は何ら不当なものではないこと、上記処断刑の問題については、かすがい部分(訴因外の事実)に立ち入って審理判断し、かすがい部分を起訴した場合の処断刑を超える宣告性を禁止すれば足りることから、かすがい外し起訴も、事案の軽重、立証の難易等諸般の事情を考慮して合理的な裁量の範囲内であるといえる限り許されると解すべきです。
かすがい部分(住居侵入)に立ち入って審理判断することについて
かすがい部分は訴因変更手続を経ていない訴因外の事実ですが、被告人を同事実で有罪とするわけではなく、量刑事情として考慮するに過ぎないため、訴因制度の趣旨に反しないと解します。

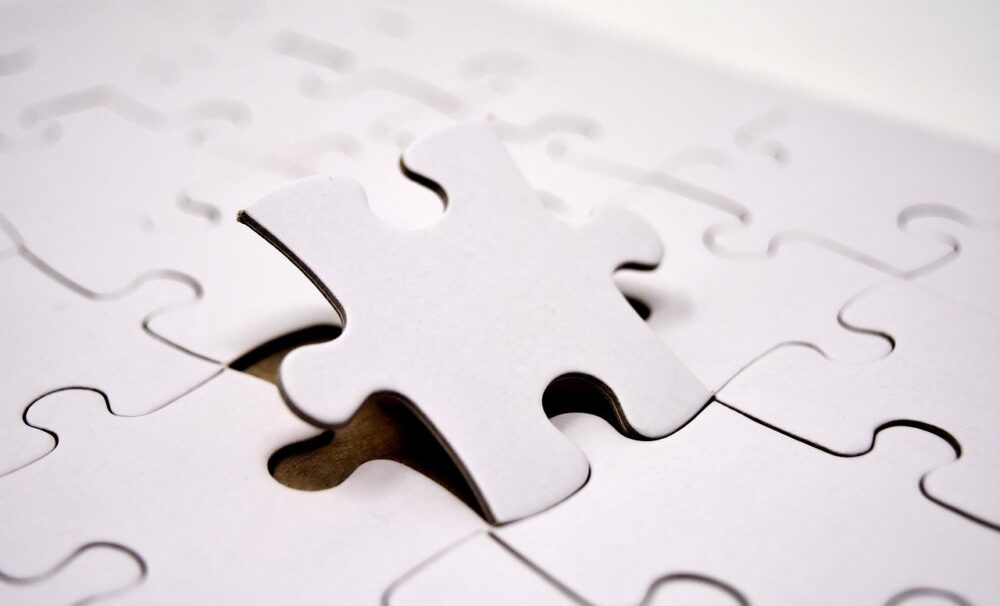


コメント