意義
「時効」とは、時間の経過という事実に一定の法的効果を認めている制度のことをいいます。
民法で認められている時効の制度は、2つあります。
① 取得時効(民法162条):一定の時間の経過によって「権利を取得する」制度
② 消滅時効〈民法166条):一定の時間の経過によって「権利が消滅する」制度
制度の趣旨
時効制度がなぜ存在しているのでしょうか。
時効制度が正当化される理由は大きく分けて3つあります。
① 継続した事実状態を保護すること
② 権利の上に眠る者は保護に値しない
③ 過去の事実の立証困難を回避する
継続した事実状態を保護する
ある事実状態が続くと、周囲の人々は「今ある事実状態」を真の権利状態であると考えます。
そのため、継続された事実状態を前提として様々な法律行為が行われることになります。
それにもかかわらず、真の権利状態は事実状態と異なるとして覆してしまうと、様々な法律関係に影響をあたえ、関係者に不利益を与えてしまうことを予想されます。
権利の上に眠る者は保護に値しない
長期の間、自分の持っている権利を放置し続けている人を保護する必要はなく、権利を奪われたとしても仕方がないという考えです。
過去の事実の立証困難を回避する
事実状態が長く続くと、時間の経過によって過去の事実を立証するための資料は失われていきます。
その一方で、 ある事実状態が続くと、周囲の人々は「今ある事実状態」を真の権利状態であると考え、その可能性が高いといえます。
保護されるべき長期の事実状態を持った者が、証拠がないために立証ができずに裁判に負けて不利益を負う危険性が生じてしまいます。
そこで、訴訟での立証困難を回避して、権利者を保護するために時効制度が存在すると考えます。
時効の効力
民法144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の効力は、「起算点」にさかのぼります。
土地を時効取得した場合、その土地は「起算点」つまり「占有開始の時点」から、時効取得者の所有物であったことになります。
また、時効の起算点は、当事者の意思で自由に選択することはできません(起算点固定の原則)。
時効の援用
民法145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
時効の期間が経過したからといって、時効の効果が生じるわけではありません。
時効の利益を得るかの判断は、当事者の意思に委ねられています。
民法では、時効の利益を得るために時効を「援用する」必要があります。
そして、民法145条で時効を援用することができる人物を「当事者」に限定しています。
「当事者」の概念については、「時効取得」と「消滅時効」で少し異なります。
「取得時効」の「当事者」:権利の取得につき 直接の利益を受ける 者
「消滅時効」の「当事者」:権利の消滅につき直接の利益を受ける者
時効利益の放棄
民法146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
時効の利益を受けるかは、当事者の意思に委ねられています。
そのため、「時効の援用」によって、①「得る」選択をすることも、②時効の利益を「放棄する」ことも可能です。
民法146条は、時効の利益を放棄するための規定であるともいえます。
「あらかじめ」とは、時効完成前のことを指します。つまり、時効完成前に時効利益を放棄することはできないと民法146条では規定しています。
時効完成前に「時効利益の放棄」が禁止されているのは、債権者が債務者に対して自分の有利な地位を利用して、債務者に時効利益を強制的に放棄させる危険性があるためです。

「じゃあ、300万円貸してあげるわ」
「しっかり、1年後に返してね?」
「あと、返してもらわないと困るから、先に時効利益を放棄してちょうだい」
『300万円を借りるためには、先に放棄しないといけないのか・・・」
「もちろん、返すつもりだから時効利益は放棄するよ」
「その条件で、300万円を貸してくれ」


「わかったわ」
返済期日から5年経過した後・・・
「5年経過したから、時効を援用して債権を消滅させたことにしたい!」
「他にもたくさんの借金があって大変なんだ」


「他の借金なんて関係ないわよ」
「そもそも、私との契約は、はじめから時効利益は放棄する前提で契約しているわ」
「・・・はい。・・・そうでした・・・ね・・・。」

このようなことにならないように、時効利益の放棄を禁止しています。
時効障害
▽時効障害については、以下の記事を参照ください。
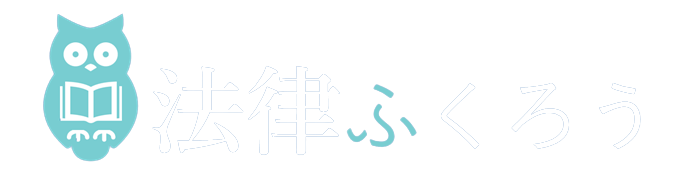




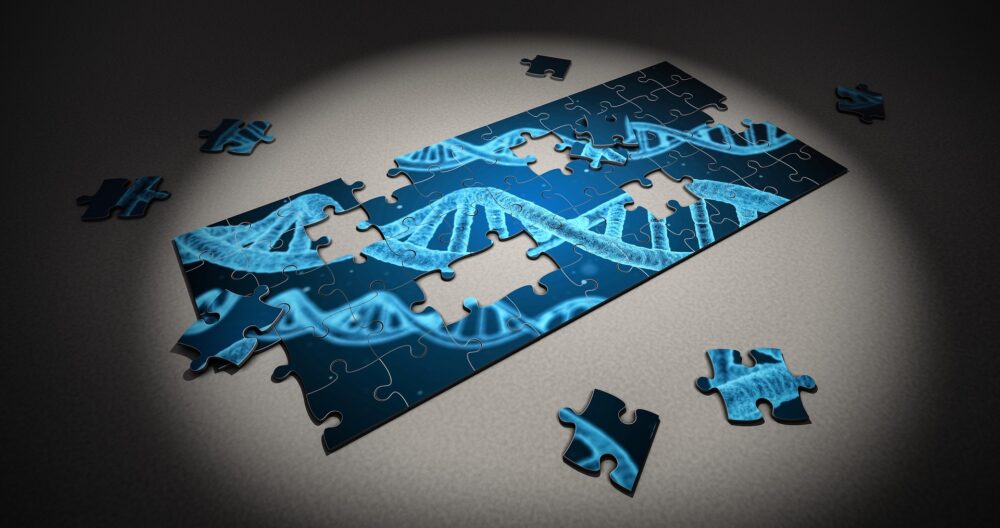
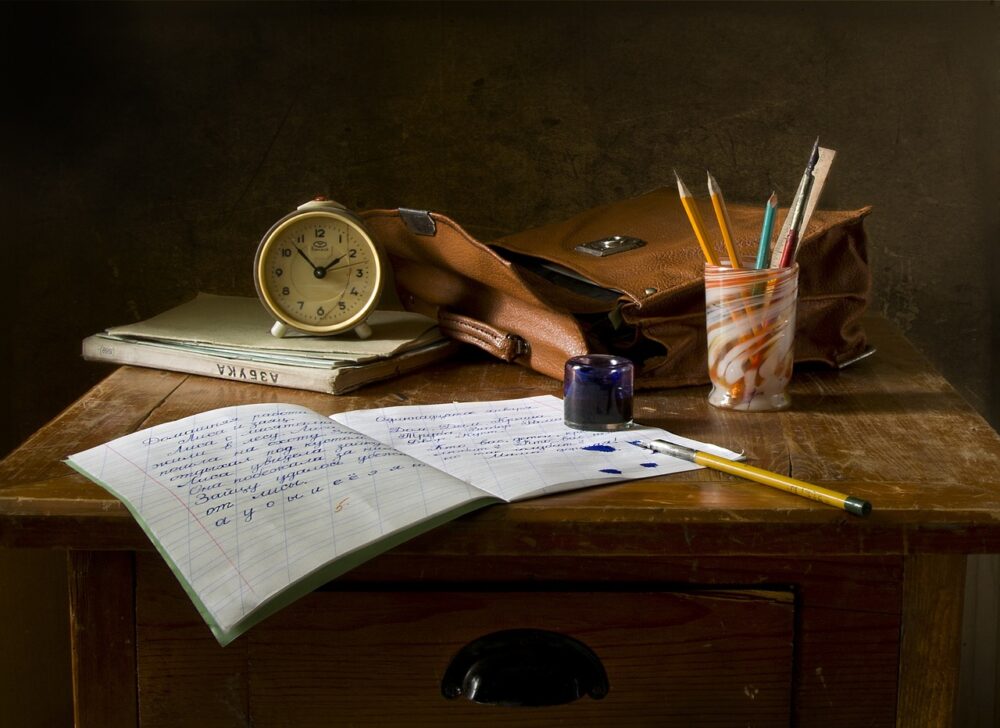
コメント