意義
「物権」とは、「物」を「支配」する権利のことを指します。
物権の対象は、原則として「物」(「ブツ」と読みます)です。
※ 権利質など、債権を対象とするものも一部あります。
「支配」とは、物が持つ「価値」、そしてその物から生じる「価値」を把握することを意味します。
この物自身が持っている価値のことを「利用価値」といい、その物から生じる価値のことを「交換価値」といいます。
「利用価値」:物を自らまたは他人に使用させて収益を得ることができる「物」の価値をいいます。たとえば、物を貸して賃料を得ることなどをいいます。
「交換価値」:物を他人に譲渡して収益を得ることができる「物」の価値をいいます。たとえば、物を目的とした売買契約を締結して、売買代金を得ることなどをいいます。
物権の種類
民法175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
物権は、新しく創設することはできません。また、法律に規定されている「物権」の内容を変更することもできません。
このような原則のことを「物権法定主義」といいます。
「物権法定主義」の結果、物権は法律で規定されたものに限られます。物権の種類は以下の通りです。
○ 所有権(民法206条)
○ 占有権(民法180条)
用益物権
○ 留置権(民法295条)
○ 先取特権(民法303条)
○ 質権(民法342条)
○ 抵当権(民法369条)
担保物権
○ 地上権(民法265条)
○ 永小作権(民法270条)
○ 地役権(民法280条)
○ 入会権(民法294条)
所有権
「所有権」は、物の価値を全て支配することができる権利です。
そのため、所有権は「利用価値」と「交換価値」の両方の価値を有します。
物権には、「用益物権」と呼ばれるものと「担保物権」と呼ばれるものがあります。これは、上記の「価値」のいずれかが制限されている物権のことを指します(制限物権)。
○「利用価値」のみを有しており「交換価値」を持たない物権を「用益物権」といいます。
たとえば、地上権が「用益物権」にあたります。
地上権は、「土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する」(民法265条)と規定されていますから、「利用価値」を有しています。
一方で、地上権は、「他人の土地」(民法265条)であることが前提なので、その土地自体を処分することはできません。そのため、「交換価値」を持っていないと評価できます。
○「交換価値」のみを有しており「利用価値」を持たない物権を「担保物権」といいます。
たとえば、抵当権が「担保物権にあたります。
抵当権は、「担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」(民法369条)と規定されています。これは、担保権者が 担保目的物を 競売することによって、不動産を換価することができることを示しているので、抵当権は「交換価値」を有しています。
一方で、抵当権は、非占有物権であって、原則として物を貸して価値を生み出すことなどはできません。そのため、「利用価値」を持っていないと評価することができます。
法典にない新たな「物権」
「物権法定主義」(民法175条)があるため、物権を創作することはできません。
しかし、実社会では法律の規定にない「物権」があります。以下のようなものがあります。
○ 水利権 「特定の目的(水力発電、かんがい、水道等)のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流水を排他的・継続的に使用する権利」(国土交通省引用)
○ 湯口権 温泉地より引湯して使用する権利
○ 譲渡担保 債権を担保するために物の所有権を債権者に移転させること
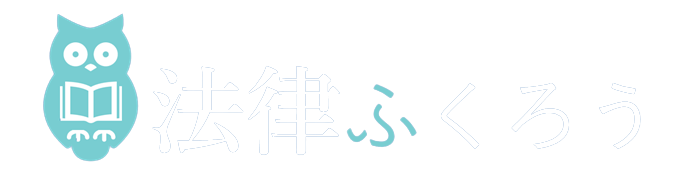




コメント